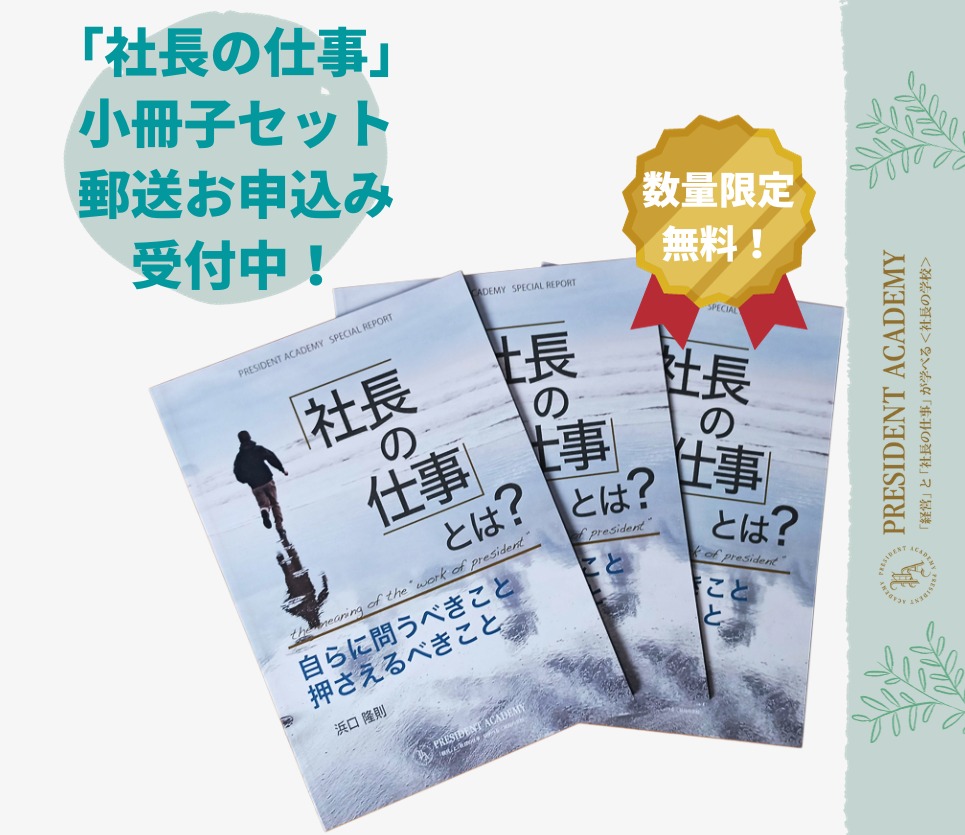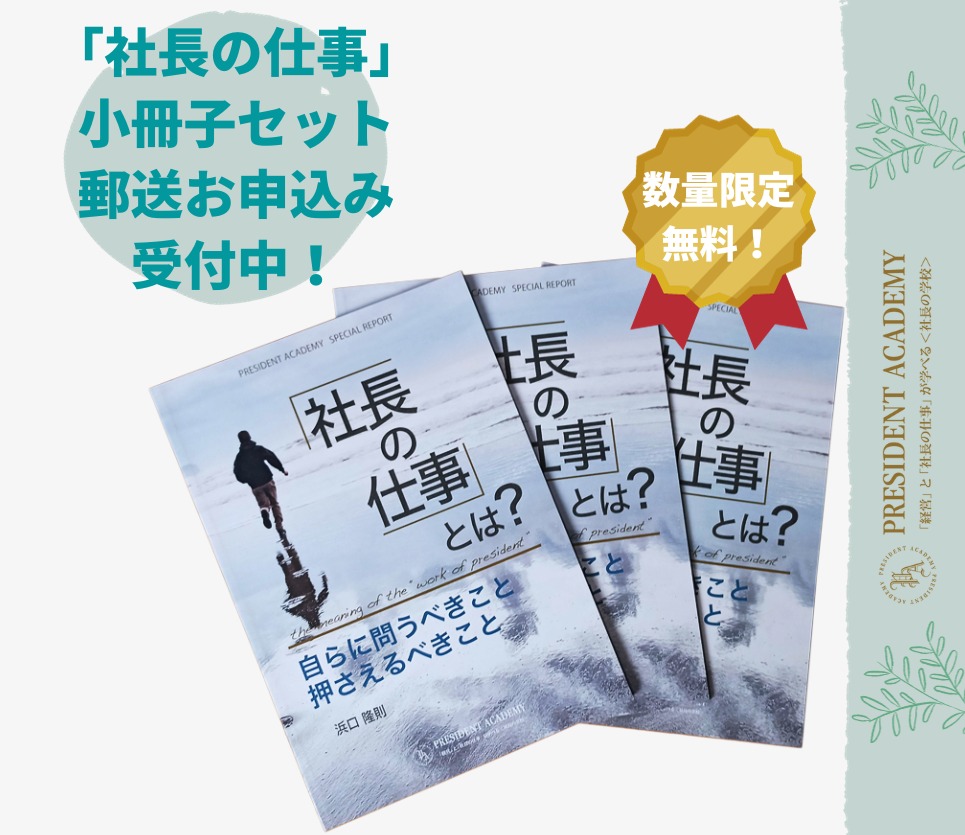ブログリレー7日目です!
こんにちは。ばあごはんエンジニアの遠藤です!
よしみさんからバトンを受け取りました! よしみさんの記事をまだ読んでいない方はこちらから読めます!ぜひご覧ください^ ^
ばあごはんとは、「シニア」×「学生」の多世代間交流を目指すマッチングサービス会社です。
早速ですが、本ブログでは、ばあごはんのWebエンジニアである私が、実践起業インターンREALを通して、
1. 「起業経験」をすることに、何を期待していたのか
2. 「起業経験」をしたことで、何を得られたのか
についての二章立てでお話しできたらと思います。
1. 「起業経験」に、何を期待していたのか
はじめに、私がばあごはんに加入した理由についてお話しします。
2019年の11月の早稲田大学の文化祭にて、私は、ばあごはん副代表の三富さんが「ばあごはんメンバーの募集」を呼びかけていたところに飛び込み参加しました。
他のメンバーとは違い、2ヶ月ほど遅れての事業参画でした。
私が「ばあごはん」に参画した理由は、2つありました。
1つは、大学生活の中で、何か実践的なスキルを身につけておきたい思いから、「ホームページを作成するスキルを活かしたい」といった理由で、もう1つは、小さい頃から祖父母にお世話になっていた経験から「多世代間交流が少なくなっている現状を変えたい」といった理由でした。
特に、前者の「Webサイトを作ってみたい」という思いはかなり強かったです。
ですから、当時の私は、「Webエンジニアとしてホームページを作って仕事をする」ものだと思っていました。
「Webエンジニアとして、ばあごはんのホームページを作るだけでお客さんが寄ってくる。」そんなことを思っていたのかもしれません。
しかし、皆さんもお察しの通り、「起業」は甘くありませんでした。
そもそもばあごはんのホームページを作り上げたところで、誰が見てくれるのでしょうか。
また、「自分たちが思う素晴らしいサービス」を1つ考えたとして、誰がそのホームページを見て自分たちが考えたサービスを試そうと思うのでしょうか。
そうなのです。例え素晴らしいサービスでも、適切なカスタマーには辿り着かなかないということに気づいたのです。
私は「Webエンジニアとしてホームページ作成をすること」を期待していましたが、起業におけるエンジニアという役職とは、もっと大きな役割を担っていたのです。
そして、結果として、「Webエンジニアとして仕事をすること」はもちろん、それ以外の部分での大きな成長を私は遂げることができたと感じています。
次の章では、実際にWebエンジニアである私が「起業を通して何を得られたか」について語ります!
2. 「起業経験」をしたことで、何を得られたのか
前章では、起業をする際、「ばあごはんエンジニアはもっと大きな役割を担っていた」と述べました。
本章では、私が「起業経験」をしたことで得られたことについて、大きく2つに分けてお話しします。
1つは、プラットホームという考え方、もう1つは、Webエンジニアとしての実践的なスキルです。
プラットホームという考え方
はじめに、プラットホームという考え方についてです。
早速ではありますが、皆さんは「プラットホーム」という言葉を聞いたことがありますか?
「プラットホームを持っていること」は事業を展開する際に大きな力を発揮しますが、プラットホームの説明をするための導入として、まずは、ばあごはんにおける「新規事業の展開の仕方」について説明させてください。
1. 最初は、問題意識・調査から仮説(サービス)を1つ作る段階です。このような仮説を俗にプロトタイプと呼んだりします。
2. 次に、実際に顧客にサービスを使ってもらう段階(検証)です。プレスリリースを公開後、ばあごはんでは、1人1人、顧客を探しに行き、検証をさせてもらいました。
3. 最後に、顧客からレビューをいただき、仮説(サービス)の改善・今後の展望を考えます。
この流れを、納得のいくサービスができるまで繰り返します。
これらの「プロトタイプ」を何回も繰り返すのではなく、1つのサービスに特化してPDCAを回し続ければいいのでは? そう思う方は、多いと思います。
しかしながら、私たちは、仮説検証を繰り返し行いました。
では、仮説検証を繰り返し行うことによって、何を得られたのか?
それは、「ばあごはんに理解を示してくれる人」を得られたこと、この一点に尽きます。
実は、このような顧客のニーズを捉えた仮説検証を繰り返していくことが、私たち「ばあごはん」を応援してくれる「場所」を作り出すことに繋がっていました。
このような場所を「プラットホーム」と呼んでいます。
ばあごはんのようなC2Cサービス、B2Cサービスは、「顧客の獲得」が大変重要になります。
プラットホームの考え方を理解し、実際に幅広い世代と関係を持つことができたことは、ばあごはんにとって、大きな財産と言えるでしょう。
「プラットホーム」を作っていくために活動した内容の詳細は、こちらからご覧になれます!
Webエンジニアとしての実践的なスキル
次に、Webエンジニアとしての実践的なスキルについてです。
私は以前、Webサイトを作る会社に務めていた経験があります。
実は、Webサイトを1つ作るのには、多くの人が関わっています。
営業、見積もり、ワイヤー設計、デザイン創案、コーディング業務、発注作業、マニュアル作成、定期メンテナンスなどです。
私はこれまで、コーディング業務以外は、携わる機会がありませんでした。
しかしながら私は、ばあごはんに入ってからコーディング業務以外の部分も、全て関わらせてもらいました。
というのも、ばあごはんは、「ITでシニアを繋ぐ」という事業を展開し、Webサイトを作成する案件をいただいていたからです。
Webサイト作成の全貌を知らなかった私にとって、ここで得られたことは計り知れません。
何せ、人数が少なかったこともあり、「営業、見積もり、ワイヤー設計、デザイン創案、コーディング業務、発注作業、マニュアル作成、定期メンテナンス」を1通り経験させてもらったからです。
これは、起業をしたからこそあり得る話だと思います。
また案件を受注した時は、他のメンバーにコンテンツについて考えてもらったり、顧客とのやりとりを見守っていただいたりと、不慣れな部分を大きく支えてもらいました。
以上2つが、ばあごはんのWebエンジニアである私が、実践起業インターンREALを通して学んだことになります。
これらの実践的な内容は、これからの私の原動力になっています。
何よりも、この事業を1年間遂行できたのも「ばあごはんメンバー」のおかげです。この場をお借りして感謝申し上げます!ありがとうございます!
さて、長くなってしまいましたが、最後にまとめです。
「起業経験」をすることに、何を期待していたのか?
(答え):Webエンジニアとしてホームページを作成すること
「起業経験」をしたことで、何を得られたのか?
(答え):プラットホームという考え方・Webエンジニアとしての実践的なスキル
以上になります。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。今後のばあごはんにもご期待ください^ ^
明日はまあやさんです!まあやさん、よろしくお願いします!
ばあごはん各種リンクはこちら↓
【ライター】
ばあごはん事業部 早稲田大学先進理工学部2年 遠藤竜仁
機械学習やWebマーケティングに興味がある。典型的なおじいちゃん・おばあちゃん子。
ばあごはんWebサイト:https://bagohan.wordpress.com/