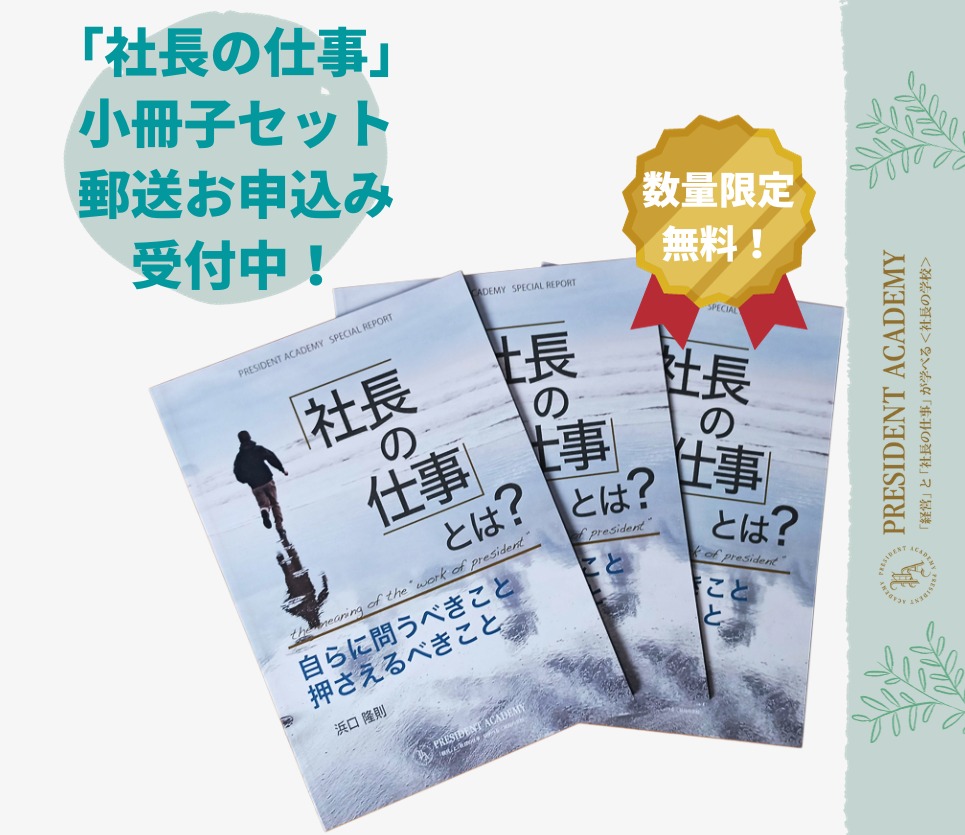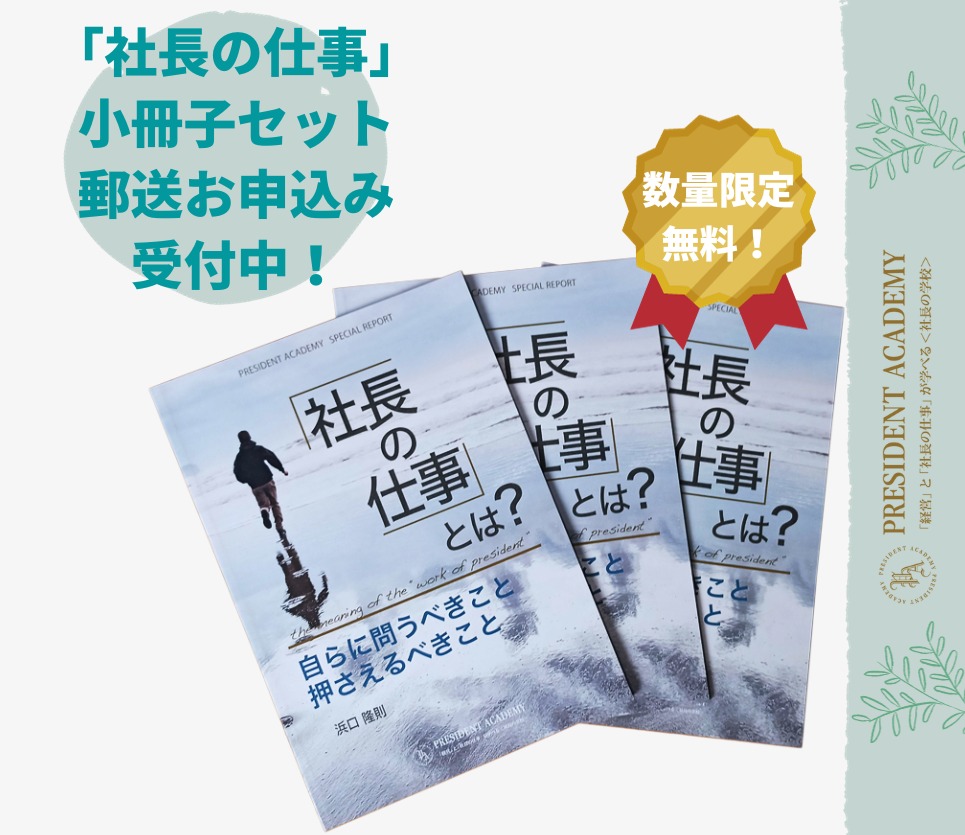経営の現場で”模倣”を活用するためのポイント
2016年1月28日@渋谷にて、早稲田大学の井上達彦教授による『模倣の経営学』セミナーを開催しました。本ページでは井上達彦教授のセミナー内容から、「経営の現場で”模倣”を活用するためのポイント」をご紹介します。
< 目次 Contents >
1.模倣を考える Good or Bad
模倣とはなにか?
模倣が勝つ理由とは?
悪い模倣とは?
良い模倣とは?
2. 模倣ベースのイノベーション Imitation based Innovation
模倣の事例:ニトリホールディングス
ニトリはなぜ高収益なのか?
模倣すべき3つの種
模倣するときに気をつけるべき3つ注意点
3. 意外なお手本の分析 Beyond Usual Suspects
既存事業を分析する
成功のコツは垂直的な模倣をすること
垂直的な模倣「3つのステップ」
模倣に対する固定観念的な考え方を変える
1.模倣を考える Good or Bad
模倣とはなにか?
模倣と聞くと「パクる」「二番煎じ」など、少しネガティブなワードをイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし、「学ぶ」の語源が「真似る」であるという説があるように、模倣は他の事例から学ぶことでもあるのです。
模倣が勝つ理由とは?

経営・ビジネスの世界では”模倣”は肯定されることも多いことをご存知でしょうか。模倣者に対して、一番手で市場を切り開く「イノベーター企業」がアプローチできる市場は、「イノベーション普及理論」における2.5%の消費者に過ぎません。残りの97%以上は「迅速な2番手」に残された潜在市場となるのです。
つまり正しい模倣の仕方を身につけ、「迅速な2番手」になることで、イノベーターが切り開いた97%以上の市場でビジネスを展開することができるのです。
「悪い模倣」「良い模倣」とは?
「悪い模倣」とは「幼稚」「低技術」「タダ乗り」といったイメージでしょうか。それに対して「良い模倣」は一見すると「オリジナル」であり、「ブランド力がある」企業と言われています。しかし、実はこれらの企業も他の企業を”模倣”しているのです。「悪い模倣」と「良い模倣」はなにが違うのでしょうか。その答えを読み解いていきたいと思います。
2. 模倣ベースのイノベーション Imitation based Innovation
模倣の事例:ニトリホールディングス

ニトリホールディングス社長の似鳥昭雄氏は模倣に対して大変肯定的な考えをお持ちの経営者です。実際にニトリホールディングスでは2つのモデルを模倣して現在のビジネスの骨格を作り上げていきました。
【モデル 1:アメリカの発明】
チェーンストア化:チェーンストア研究会から他のチェーン店展開手法を模倣
日本では「少店舗数」「高価格」「アイテム別の陳列展示」が常識となっていました。それに対してアメリカでは「200店舗以上が当たり前」「低価格(日本の3分の1」「ライフスタイル展示」が常識でした。
似鳥氏はアメリカへ視察へ行き、アメリカのビジネスモデルを模倣して取り入れていったのです。
【モデル 2:異業種の手法】
家具の自社生産:自動車メーカーの品質管理を模倣
上記のチェーンストア化を模倣し、自社生産に踏み切ることで、次に課題となったのが品質管理でした。家具は「事後対応」が基本となっており、完成後に検品して不具合があれば直す体制でした。そこで似鳥氏が模倣したのが自動車製造の品質管理です。自動車製造では検品・検質・検量なしが基本で、「検品は二度手間」と考えられていました。似鳥氏はその考え方を模倣し、「事前対応」を徹底するようにしたのです。
ニトリはなぜ高収益なのか?
売上高 :387,605(百万円)2014年2月
経常利益 :63,474
経常利益率:16.38%
従業員数 :正規従業員2,873名 パートタイム 6,974 名
27期連続増収増益
ニトリホールディングスの業績は、疑う余地が無いほど優秀な数字です。なぜ、ニトリホールディングスはこれほど高収益なのでしょうか。要因は「模倣できない仕組み優位を構築した」からです。
ニトリは家具の販売はもちろん大きな収益源ですが、より大きな収益をあげているのは別の商品です。それは「ホームファッション」という“表の価値”です。枕カバーやカーテンなどの「おしゃれなアイテム」が、実は大きな収益になっているのです。そして、この“表の価値”は一般消費者や競合企業ももちろん理解できますし、模倣しようとすればそれほど苦労なく模倣可能だと思います。しかし、ニトリが持つ「模倣できない仕組み」は、前述の「チェーンストア化」と「品質管理」にあるのです。
ここには、「模倣できない仕組みは、実は模倣から生まれた」という矛盾があります。井上達彦先生はこれを「模倣のパラドックス」と呼んでいます。
模倣すべき3つの種
今回はニトリホールディングスを例として取り上げていただきましたが、ユニクロやクロネコヤマトなど日本を代表する企業も、実は”模倣”を活用しています。井上達彦先生が”模倣”を活用して成功している企業を分析した結果、以下の3つを”模倣”すると成功する確率が高いことがわかってきました。
① 異国のビジネス
② 異業種のビジネス
③ 過去のビジネス
つまり、「遠い世界のお手本がイノベーションをもたらす」ということです。
模倣するときに気をつけるべき3つ注意点
今回のセミナーで井上達彦先生がご紹介してくださった、模倣の実践者の考えを3つご紹介させていただきます。
①「すぐに頭に思い浮かぶものを集めるな(Beyond the Usual Suspects)」
②「異業種の方が仕組みはみつけやすい」
紳士服チェーンや百円ショップなど、気になったところは何でも見に行きます。料理と違って、経営の仕組みはどの業界からも学べます。むしろ、飲食とは全く異なる業界のほうが、固定観念を持たずに見られる分、ヒントを見つけやすい。
3. 意外なお手本の分析 Beyond Usual Suspects
既存事業を分析する
模倣をしようと思ったら、まず対象の会社(業態)が「誰に(顧客)、何を(価値)、いかに(方法)提供していたのか」を明確にすることから始めます。この時に気をつけなければならないのは「見えやすい本質的な要素」だけではなく、「見えにくい構造的な要素」まで目を向けるということです。一人で考えてもなかなか良い視点は得られにくいので複数人で、ブレスト的に要素を出していくことをオススメします。
成功するコツは垂直的な模倣をすること

成功のコツは垂直的な模倣をすることです。つまり、良い模倣とは垂直的な模倣はイコールなのです。
一橋大学大学院教授の楠木建氏はこう言っています。
「良い模倣が垂直的な動きであるのに対して、悪い模倣は水平的な横滑り」
上図のようなオブジェクトの並びがあったら、「左から準に大きくなりながら2つのパターンを繰り返す」と抽象化して特徴を捉えます。そしてそれを他のオブジェクトで実装するのです。横滑りの模倣ではなく、垂直的な模倣を実践する方法を簡易的にまとめると以下の3つのステップがあります。
垂直的な模倣「3つのステップ」

① 異国・異業種のビジネスを抽象化する
② 収益原理を理解する
③ 自社のビジネスに導入・適用する
この垂直的な模倣をいかに実現するかが「模倣の経営」を成功させられるかどうかの分かれ道になります。
4.まとめ
今回の井上達彦先生のセミナーを実践していくためには2つ、必要なことがあります。それは「模倣に対する固定観念的な考え方を変える」ことと、「垂直方向に行き来する能力を高める」ことです。
模倣に対する固定観念的な考え方を変える

「模倣はイノベーションと対極的なところにあるもの」と考えられがちですが、そうではありません。むしろ「模倣はイノベーションの過程にあるもの」だと考える必要があります。まずは”模倣”に対する考え方を変えていきましょう。
垂直方向に行き来する能力を高める
垂直的な模倣「3つのステップ」でご紹介させていただいたとおり、様々な会社をの要素を抽象化・分析し、自分のビジネスに持ってくるという作業を数多くこなすことが大切です。世の中には無数の会社があります。そのどれもがうまくいっているわけではありませんが反面教師として「反転模倣」することもできます。まずは今回井上達彦先生にご教授いただいた「正転模倣」を成功企業に適用して自社に活かすことを繰り返し考えてみましょう。模倣する能力は今後も求められる経営者としての実力です。ぜひこの「模倣する能力」を高めていきましょう。
井上達彦先生、素晴らしい内容をありがとうございました。